 |
|||
|---|---|---|---|
今回水槽を新規導入するに当たり、水槽台が一つの問題となっておりました。 もちろん金銭面からですが... なので自作を決意し製作に取り掛かりましたのでその模様を。 水槽台は住宅や水槽を守るとても大切なものですから、 水槽台を専門に扱われているショップなどに発注するのが1番安心でオススメです。 もしこれを参考に製作される方がおられましたら自己責任でお願いいたします。 水槽台のサイズは幅121cm×奥行き61cm×高さ40cmになります。 1cmずつ大きくしたのは、自作での多少の誤差を計算に入れたものですね。 こうすることにより多少の誤差は誤魔化せますからw 今回の製作での拘りは、 まず高さです。 この高さ40cmは我が家の観察スタイルにピッタリで、掃除もやりやすい高さです。 普段胡坐をかいて観察したり椅子に腰掛けて観察していますのでこの高さに拘りました。 そして、最大のこだわりは重量の分散。 完成したものが100%の分散がされているかは謎ですが、 自分なりにかなり考えて設計しましたので、自己満足度は非常に高いですね。 これからの月日の経過でどうなるかがこれからの焦点となります(汗。 |
|||
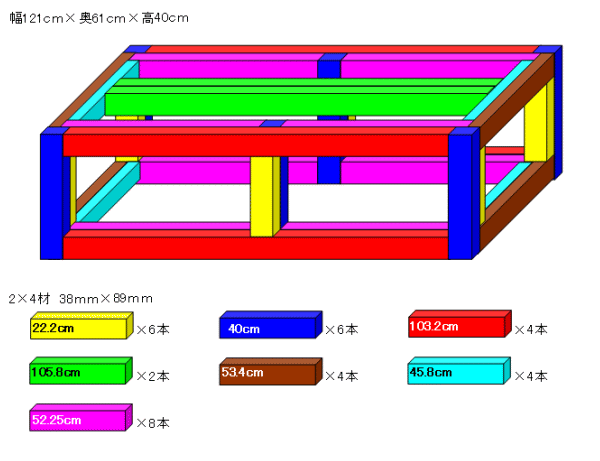 |
|||
| 設計 上記は自分なりに考え抜いた設計図になります(汗。 Excelを利用して簡単に作成したものです。 製作するときはあらかじめ設計図を作成し、大体のイメージと木材の利用数・サイズなどを把握しておく必要があります。 これをすることにより作業がかなりはかどります。実際作りながら考えるのは失敗の原因になると思います。 これにビス打ちをするところに印をするともっといいですね〜。 この組方なら満遍なく重量がコンパネへとかかり、更にコンパネが重量を分散してくれるという感じです。 |
|||
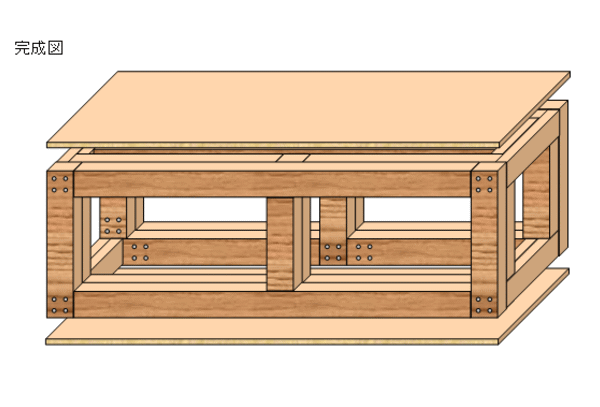 |
|||
| 完成図 上記は完成図です。 ご覧の通りコンパネをかませて完成です。 この図はビス打ちの場所を付け加えましたが、この通りにはならなかったですね〜(汗。 より強度を求めるとこれだけでは少し??でしたから(汗。 |
 |
材料 今回は上記設計図どおり2×4材のみでの製作です。 この材の長さは色々ですが、サイズは規格がありますので、設計時にも助かりますね。 カットはホームセンターでやってもらえますので、そちらでやってもらうのが手間も省けオススメです。 ...が、今回僕がやってもらった所はカットが甘くサイズが多少ずれてまして苦労しました。 ですので、皆さんもカットしてもらう場合は信用のあるところでやってもらいましょう(汗。 後はコンパネ2枚・ビスなどを購入し合計は約7,000円ほどです。 自作はかなり安くつきますwこれが自作の魅力♪ |
 |
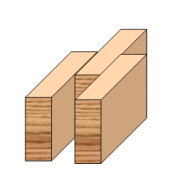 |
あると便利 自作には電動ドリルを使用されることをオススメします。 かなりのビス打ちをしますので、手作業では大変です。 あると便利と言うよりは無くて後悔という感じでしょうか? もう一つは左のもの。 木材のハンパが出ますのでそれをもらい、ビス打ちしたものです。 これで木材を立てたり、直角を計れたりと何かと便利です。 |
|
 |
 |
作業工程1 順序は特に決めていませんでしたが、取っ掛かりとして解りやすいところから作りました。左写真が上記のハンパで作った物で、挟んで木材を立てています。 これを2本並べてその上にあらかじめ接続場所を記しした木材を置き、ビスで固定しました。これが高さもあって大変でした(汗。 ビス打ちするときはあらかじめドリルで穴を開けておくと木が割れにくく作業もしやすいです。 両端を固定しないのは後々外枠へ固定するときにズレを調整する為です。このパーツが水槽の底面を支える重要なところになります。 |
|
 |
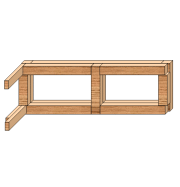 |
作業工程2 途中の写真ですが、水槽台の下の部分です。 イメージ画像の用なものを2セットつくり最後に抱き合わせる感じです。 作業は常にメジャーで計りながら正確に作っていかないと、抱き合わせ時に痛い目にあいます。 要は常に木材を仮組みしながらの作業をしなければなりません。 とにかく角の部分が直角になっているか?これだけは正確に測りながら製作しましょう。 |
|
 |
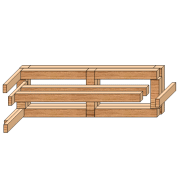 |
作業工程3 そろそろ終盤です。 これが最後の難関(汗。まずは作業1のパーツを2のパーツ片方のみに固定します。その後1の固定されていない方へ木材を固定します。 このときにしっかり水平を保つように固定しないとこの上部パーツが全く機能しなくなりますので、細心の注意を払ってください。 |
|
 |
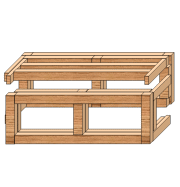 |
作業工程4 最後にもう一方の2のパーツを抱き合わせて完成です♪ 左の写真は上記の作業中の画像ですが、上部中央の2本の木材を支える材が歪んでいましたので、この様に水平を保てませんでした。 ですので、固定するときにかなりの力技で何とか水平を保つように押し込んだと言う形です(汗。 この辺りは木材の柔軟性に助けられたと言う感じですね。 |
|







